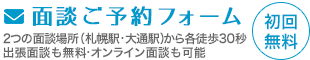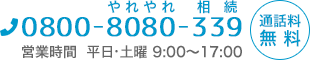相続人がいない場合とは、配偶者がなく(死別した場合、離婚した場合を含む)、かつ、子も直系尊属(父母など)も兄弟姉妹・甥姪もいない(亡くなっている場合を含む)ケースです。
この場合、法定相続人がいませんので、被相続人の遺産は最終的には国庫にわたることになります。
しかし、自分の遺産が国庫にわたることに納得がいかない方もいるのではないでしょうか。
国庫にわたるくらいなら、法定相続人以外の親族や、御世話になった第三者、自分が支持する会社や団体などに、遺贈(遺言によって遺産を渡すこと)した方がよいと考えるケースです。
しかし、遺言が無い場合には、この希望が叶えることはできません。
相続人がいない場合で、第三者などに遺産を渡したい場合には、遺言を作成するのが第一の選択肢です。
この場合に注意しておかなければならないことは、いくつかあります。
1つには、受遺者は遺贈は放棄(遺贈をもらわないという選択)することができる、ということです。
遺贈が放棄されてしまえば、その遺産はもらい手が無くなり、最終的には国庫にわたることになってしまいます。
ですから、遺贈をする場合には、事前に受遺者となる方に、了解をとった上で行った方がよいでしょう。
また、受遺者(遺贈を受ける人)にも、法定相続人が相続する場合と同様に、相続税が課されることにも、注意する必要があります。
さらには、遺言の中で遺言執行者を指定しておくと、他の相続人等の協力が無くても、遺言執行者が単独でスムーズに遺言の通りの相続手続きを行う(遺言の執行、といいます)ことができますので、残されたご家族の負担をさらに軽減することが可能です。
遺言執行者は、ご家族の方を指定することもできますし、当センターの行政書士のように利害関係の無い第三者を遺言執行者の指定することもできます。
利害関係の無い第三者を遺言執行者に指定することにより、遺言の内容に不満を持っているご遺族から妨げられることなく、遺言の執行を進めることができ、遺言の通りに相続手続きが行われないリスクを限りなくゼロに近づけることができます。
当センターの行政書士に遺言執行者を任せたい、または、(遺言の執行が大変なので)遺言執行者の代理人になってほしい、という場合には、当センターの行政書士にご相談ください。
詳しくは当センターの行政書士による[遺言執行者への就任]の内容と料金をご覧ください。