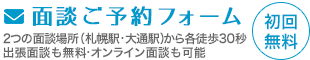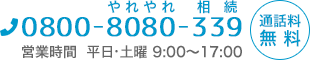日本の法律では、同性婚は認められていません。
したがって、同性婚のパートナーには、一切の相続権がないことになります。
どんなに長い間連れ添っていても、異性同士の法律婚(戸籍を入れている婚姻)でなければ、相続に関しては他人と同じ扱いになります。
同性のパートナーは、法定相続人にはなれないのです。
そこで、同性のパートナーに財産を残したい場合には、法律婚の配偶者の場合と異なる、別の方法が必要です。
その方法の1つ、第一の選択肢が遺言です。
遺言では、法律上、相続人ではない人に対しても、遺産を渡すことが指定できます(遺贈)。
遺言で遺贈をしておくことで、自身が亡くなった後、同性のパートナーに遺産を残すことができるのです。
ただし、遺言で遺贈をする場合でも、同性のパートナーと、法定相続人が疎遠であったり、不仲な場合には、遺産を分ける割合について配慮が必要です。
同性のパートナーと法定相続人の間には、利害の対立、紛争が生じやすいからです。
こういったトラブルを避けるためには、遺言に付言として、法定相続人に対してメッセージを残し、同性のパートナーに遺産を渡すことの理由を説明する、また、法定相続人となる人の遺留分以上は最低でも渡してあげる、といった配慮が考えられます。
同性のパートナーに財産を残す方法としては、遺言以外にも、
生鮮贈与を活用する
生命保険の受取人に同性のパートナーを指定する
特別縁故者として財産を受け取ってもらう
などの方法があります。
ただし、特別縁故者の制度は、法定相続人が一人もいないこと、亡くなった方と生計が同一であったことなど、いくつかの条件があり、ハードルが高い方法です。
遺言を作成して、遺贈をする、これが同性のパートナーに財産を残す、最もスタンダードな方法と言えるでしょう。
さらには、遺言の中で遺言執行者を指定しておくと、他の相続人等の協力が無くても、遺言執行者が単独でスムーズに遺言の通りの相続手続きを行う(遺言の執行、といいます)ことができますので、残されたご家族の負担をさらに軽減することが可能です。
遺言執行者は、ご家族の方を指定することもできますし、当センターの行政書士のように利害関係の無い第三者を遺言執行者の指定することもできます。
利害関係の無い第三者を遺言執行者に指定することにより、遺言の内容に不満を持っているご遺族から妨げられることなく、遺言の執行を進めることができ、遺言の通りに相続手続きが行われないリスクを限りなくゼロに近づけることができます。
当センターの行政書士に遺言執行者を任せたい、または、(遺言の執行が大変なので)遺言執行者の代理人になってほしい、という場合には、当センターの行政書士にご相談ください。
詳しくは当センターの行政書士による[遺言執行者への就任]の内容と料金をご覧ください。