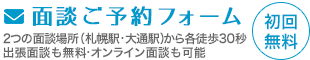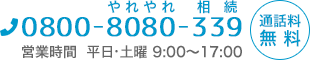現在の配偶者との間に子があり、かつ、前配偶者との間にも子がいる場合、どちらの子も法定相続人になります。
もし遺言が無い場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めることになります。
ということは、この場合、死亡時の配偶者、現在の配偶者との間の子、前配偶者との間の子が遺産分割協議を行うことになります。
※配偶者がすでに亡くなっていた場合には、現在の配偶者との間の子と、前配偶者との間の子で、遺産分割協議を行うことになります。
一般に、死亡時の配偶者および現在の配偶者との間の子と、前配偶者との間にも子との関係は疎遠であることが多いでしょう。
つまり、遺言が無ければ、疎遠な相続人同士で、遺産を分けるための話し合いをしなければならないのです。
それは、残された遺族にとって、酷であることでしょう。
また、遺産分割協議もまとまりにくいのではないでしょうか。
遺産分割協議が成立するまでは、亡くなった方の遺産をもらう(預貯金の払戻しなど)ことはできないので、場合によって、残されたご遺族(とくに配偶者)の生活が脅かされることになる可能性あります。
そのような事態を避けるには、遺言で遺産を分け方を指定しておくのが望ましいと言えます。
遺言があれば、遺産分割協議を行うことなく、相続手続きを行うことができるからです。
ただし、遺言を書く場合でも、遺留分(最低限もらえる相続分)には配慮した上で相続分を指定するようにしましょう。
それが相続人同士の紛争の予防になります。
さらには、遺言の中で遺言執行者を指定しておくと、他の相続人等の協力が無くても、遺言執行者が単独でスムーズに遺言の通りの相続手続きを行う(遺言の執行、といいます)ことができますので、残されたご家族の負担をさらに軽減することが可能です。
遺言執行者は、ご家族の方を指定することもできますし、当センターの行政書士のように利害関係の無い第三者を遺言執行者の指定することもできます。
利害関係の無い第三者を遺言執行者に指定することにより、遺言の内容に不満を持っているご遺族から妨げられることなく、遺言の執行を進めることができ、遺言の通りに相続手続きが行われないリスクを限りなくゼロに近づけることができます。
当センターの行政書士に遺言執行者を任せたい、または、(遺言の執行が大変なので)遺言執行者の代理人になってほしい、という場合には、当センターの行政書士にご相談ください。
詳しくは当センターの行政書士による[遺言執行者への就任]の内容と料金をご覧ください。