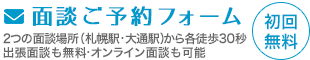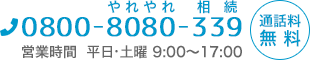遺言が無い場合には、法定相続人全員による話し合い=遺産分割協議で、遺産の分け方を決めることになります。
しかし、自分の死後、法定相続人の一部に対して、遺産を渡したくないと考える場合もあります。
例えば、親不孝の子、浪費癖のある子、疎遠・不仲の人(兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合など)がいる場合、相続税対策のためにあえて相続させない場合などです。
このような場合、その特定の法定相続人に対して、遺産が渡らないように遺言で指定することが可能です。
遺言があれば、原則として、遺言の指定通りに遺産が分けられることになりますので、遺産分割協議は必要ありません。
遺産分割協議が無ければ、遺産を渡したくない相続人が自らの相続分を主張することが自体ができませんので、結果として、「一部の相続人に相続させたくない」という遺言者の思いが叶うことになります。
ただし、注意しなければならないのは、遺留分です。
いくら遺言で自由に遺言の分け方を指定できるといっても、(兄弟姉妹・甥姪以外の)法定相続人には、遺留分(最低限もらえる相続分)というものが法律により保障されています。
遺留分を侵害するような遺言を書くこと自体は有効な行為ですが、遺留分が侵害された、つまり、最低限もらえる分より少なかった相続人は、遺留分を侵害した相続人に対して、遺留分を満たす金額を請求することができます。
相続人間で遺留分の請求が起こるのは、いわゆる遺産争いとなり、家族関係に禍根を遺すことになってしまいます。
ですので、遺言を書く時には、遺留分に配慮して作成するとよいでしょう。
具体的には、
- 遺産を渡したくない相続人にも遺留分を満たす程度は相続させる。
- 遺言の付言(自由に文言を書ける部分)として、どうして遺産を渡さないのか、その理由を記載したりするなど、遺産を貰えない相続人の感情に配慮する
などの方法です。
いずれにしても、法定相続分とは異なる遺産を分け方を実現するには、遺言を作成することが、第一の選択肢であることは間違いありません。
(他には、生前贈与、家族信託といった方法もあります)
さらには、遺言の中で遺言執行者を指定しておくと、他の相続人等の協力が無くても、遺言執行者が単独でスムーズに遺言の通りの相続手続きを行う(遺言の執行、といいます)ことができますので、残されたご家族の負担をさらに軽減することが可能です。
遺言執行者は、ご家族の方を指定することもできますし、当センターの行政書士のように利害関係の無い第三者を遺言執行者の指定することもできます。
利害関係の無い第三者を遺言執行者に指定することにより、遺言の内容に不満を持っているご遺族から妨げられることなく、遺言の執行を進めることができ、遺言の通りに相続手続きが行われないリスクを限りなくゼロに近づけることができます。
当センターの行政書士に遺言執行者を任せたい、または、(遺言の執行が大変なので)遺言執行者の代理人になってほしい、という場合には、当センターの行政書士にご相談ください。
詳しくは当センターの行政書士による[遺言執行者への就任]の内容と料金をご覧ください。