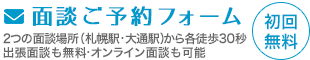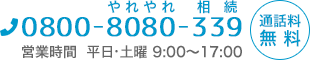このページの目次
自筆証書遺言とは?
「自筆証書遺言」とは、遺言者が手書きで(自筆で)作成する遺言書のことです。
一般に作成されている遺言の多くはこの形式です。
筆記用具や紙に制限はありませんので、印鑑があれば、すぐにでも作成することができます。
近年、法律の改正があり、遺言に添付する財産目録については、手書きでなくてもよくなりました。
遺言者が多くの種類の財産を所有している場合、遺言に、財産の1つ1つについて手書きで列挙していくのは大変です。
このような場合に、遺言の本文には「別紙財産目録に記載した不動産はAに相続させる」と書き、これにパソコンなどで作成した財産目録を添付することができます。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言のメリット
- ペンと紙があれば、手軽に作成できる
- 費用がかからない
- 遺言書保管制度を利用すれば、法務局で預かってもらえる
(遺言書保管制度を利用した場合、検認が不要)
(遺言の執行に速やかに着手できる→ただし、注意点あり(※))
自筆証書遺言のデメリット
- 専門家のアドバイスが無い場合、遺言の形式の間違いのため、無効になりやすい
- 専門家のアドバイスが無い場合、法律面や相続対策として配慮に欠けて、紛争になりやすい
- 紛失の可能性がある
- 発見されない可能性がある
- 隠蔽・破棄・変造される可能性がある
- 遺言書保管制度を利用しない場合には検認が必要
(遺言の執行への着手に時間がかかる)
法務局の「遺言書保管制度」を利用すればデメリットを避けられる
自筆証書遺言には上記のようなデメリットがありますが、令和2年に開始された「遺言書保管制度」を利用すれば、デメリットのいくつかを避けることができます。
遺言書保管制度が始まる前は、自筆証書遺言を自宅で保管している場合がほとんどでした。
しかし、自宅で保管していると、遺言が紛失したり、家族(相続人)などによる遺言の隠匿や変造、破棄の可能性や、遺言を発見してもらえないリスクがあります。
そこで、法務局が遺言の原本を保管してくれる制度(遺言書保管制度)が始まりました。
この制度によって、遺言書の紛失や隠匿・変造・破棄を防ぐだけでなく、遺言書を発見してもらいやすくなりました。
遺言書の検認とは?
自筆証書遺言を保管していた家族や、発見した人は、遺言者が亡くなった後、遺言を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認を経ないと、遺言の執行(不動産の名義変更や金融機関の預金の払戻し手続きなど)ができないため、自筆証書遺言が残されていた場合には必須の手続きになります。
検認には、相続人を確定するための戸籍を集めたり、家庭裁判所に申し立てる手続きが必要になるなど、相続人にかなり負担がかかり、しかも時間(検認の準備~検認終了まで2~3ヶ月程度)もかかります。
しかし、遺言書保管制度を利用していれば、生前に遺言を法務局に預けた時点で法律が定める形式通りであることは審査済みなので、遺言者の死亡後に検認をする必要がありません。
自筆証書遺言を作成する場合に、遺言書保管制度を利用することには、大きなメリットがあると言えるでしょう。
(※)ただし、注意点があります。
遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は検認の必要はありませんが、代わりに「遺言書情報証明書」(遺言書の内容の証明として役所や銀行などに提出するもの)という書類を法務局に発行してもらわなければなりません。
「遺言書情報証明書」を発行してもらうには、遺言者の法定相続人を証明するすべての戸籍(または、その代わりとなる法定相続情報一覧図)を提出する必要があります。
そのため、遺言者が亡くなる前に法定相続人を証明する戸籍を取得しておかなかった場合には、家庭裁判所で検認手続きを行うのとほぼ同程度の時間がかかってしまう可能性があります。
遺言者の死亡後すみやかに遺言の執行(相続手続き)を始められるように、遺言書保管制度を利用する場合には、遺言者の生前に法定相続人を証明するための戸籍を取得(2週間~2・3ヶ月程度かかる場合があります)しておくことが重要です。
自筆証書遺言が無効・紛争になりやすい理由とは?
自筆証書遺言は、その形式が法律によって厳格に定められています。
具体的には、全文(財産目録を除きます)、日付、氏名を自書し、これに印を押してある必要があります。
この形式の通りに作成されていない自筆証書遺言は、無効(遺言の執行に使えない)になってしまいます。
自筆証書遺言には、このような形式の間違いによる無効のものが少なくないのです。
また、自筆証書遺言は、行政書士など遺言作成の専門家のチェックを受けていない場合が多く、そのため、法律的に、あるいは、相続対策として、行き届いていないものである可能性が高いのです。
例えば、兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」という最低限もらえる割合が決められていますが、遺留分に配慮が行き届いていない遺言の場合、遺留分をもらえなかった相続人に不満が残ります。
そこで相続人間で遺留分侵害額請求が行われるなど、紛争のきっかけになってしまうことがあります。
自筆証書遺言を作成する場合には、遺言書保管制度を利用するととも、必ず行政書士などの専門家のチェックを受けるようにするのが賢明でしょう。
詳しくは自筆証書遺言の作成サポートをご覧ください